- 心的外傷後ストレス障害(PTSD)について
- PTSDの原因
- PTSDの症状
- PTSDの診断基準
- 子どもに見られるPTSDの症状
- PTSDの合併症
- PTSDがある方への対応
- PTSDの治療
- PTSDの経過
心的外傷後ストレス障害
(PTSD)について
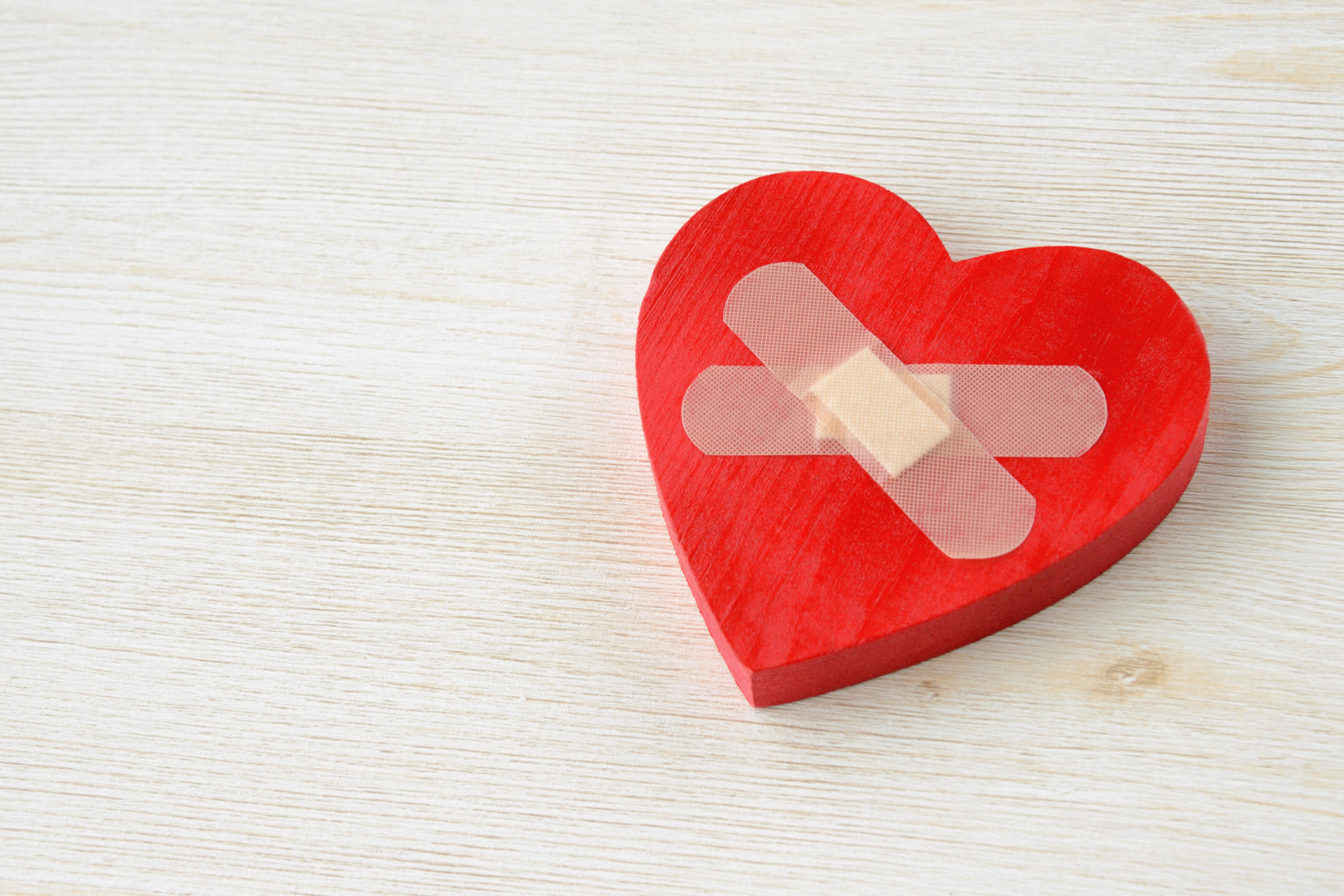 心的外傷後ストレス障害(PTSD)は、神経症性障害の一種で、強い精神的衝撃、いわゆるトラウマをきっかけに発症する心の病です。生死に関わるような重大な出来事を自ら経験したり、他者の死や深刻な被害の現場を目撃するなど、日常では想像しがたい強いストレスに晒された後に生じます。
心的外傷後ストレス障害(PTSD)は、神経症性障害の一種で、強い精神的衝撃、いわゆるトラウマをきっかけに発症する心の病です。生死に関わるような重大な出来事を自ら経験したり、他者の死や深刻な被害の現場を目撃するなど、日常では想像しがたい強いストレスに晒された後に生じます。
通常は、トラウマ体験から数週間から半年程度の潜伏期間を経て症状が現れるとされており、大規模災害における発症率はおおよそ10%と報告されています。また、PTSDは女性に多く見られ、男女比はおよそ1:2と言われています。
発症のきっかけとなる体験は、地震や火災、洪水などの自然災害、命に関わる病気の診断、交通事故、戦争、テロ、監禁、家庭内暴力(DV)、性的被害など様々です。加えて、これらの出来事を直接体験していなくても、被害者の話を聞いたり、報道などを通じて疑似体験することで発症することもあります。
心的外傷後ストレス障害
(PTSD)の原因
PTSDは、非常に強いストレス体験を受けた後に発症するとされており、その背景にはストレスホルモンである副腎皮質ホルモン(コルチゾール)の過剰分泌が関与していると考えられています。ただし、現在のところ原因について明確な結論は得られていません。
コルチゾールは、転写因子として作用し、様々な遺伝子の発現を変化させることが知られています。これにより、脳内の多くの遺伝子活動に影響を与える可能性が指摘されています。また、脳の画像研究では、PTSDの患者様において海馬の萎縮が報告されており、海馬や前頭前野の機能低下、そして扁桃体の過活動が、PTSDの発症や症状と関係していると言われています。
心的外傷後ストレス障害
(PTSD)の症状
PTSDでは、以下のような特徴的な症状が現れます。
再体験(フラッシュバックなど)
本人の意思とは関係なく、トラウマとなった体験が突然蘇ります。
記憶が急に浮かんでくる(侵入)、夢に繰り返し登場する、あるいは目の前で再び出来事が起きているかのように感じる解離反応(フラッシュバック)などが代表的です。
回避行動
トラウマに関連する場所、人物、会話、映像などを無意識に避けるようになります。
また、それに伴って過去の記憶や感情とも向き合えなくなり、引きこもり状態に陥ることもあります。
認知・感情の否定的な変化
出来事の一部を思い出せなくなる(解離)、自分や他人への信頼が持てなくなる、罪悪感や怒りが長く続く、自分を責める思考が止まらない、関心や興味を失う、感情が鈍くなる(情動の麻痺)など、心の働き全体にネガティブな変化が生じます。
覚醒レベルや反応性の異常
常に緊張していたり、些細な刺激にも過敏に反応するようになります。
不眠、強い苛立ち、突発的な怒り、衝動的・自傷的行動、集中力の低下、過度な警戒心、過呼吸、驚きやすさ(驚愕反応)などが見られます。
これらの症状は、トラウマ体験から数週間から半年ほど経ってから現れます。
心的外傷後ストレス障害
(PTSD)の診断基準
アメリカ精神医学会が定めた診断基準DSM-5によると、PTSDと診断されるには、特定の症状が1ヶ月以上持続していることが条件となります。
また、発症の引き金となる出来事については、「命の危険を感じる」「重度の怪我を負う」「性的被害を受ける」といった深刻な体験に直接関与する、または身近な人がそうした体験をしたことを知るなど、強い心理的衝撃を伴う出来事であることが明示されています。
子どもに見られる
心的外傷後ストレス障害
(PTSD)の症状
 子どものPTSDでは、大人とは異なる形で症状が現れることがあります。
子どものPTSDでは、大人とは異なる形で症状が現れることがあります。
例えば、遊びの中でトラウマ体験を繰り返し表現することがあります。また、悪夢を頻繁に見るものの、その内容がトラウマと直接関係していないケースも少なくありません。
心的外傷後ストレス障害
(PTSD)の合併症
物質依存
PTSDのある方は、不眠や不安、イライラといった苦痛な症状への対処手段として、アルコールや薬物に頼ってしまうことがあります。
このような「物質依存」は非常に高い頻度で見られ、合併率は全体の3〜5割にのぼると報告されています。
心的外傷後ストレス障害
(PTSD)がある方への対応
PTSDのある方への支援には、「心理的応急処置(PFA: Psychological First Aid)」という対応方法が推奨されています。
以下は、PFAの実践において大切とされるポイントです。
- プライバシーを尊重する
- 否定せず、無理に話を引き出そうとせずに、支持的な姿勢で耳を傾ける
- 行動や感情を一方的に決めつけない
- 解決策を押しつけるのではなく、本人が自らの力で問題に向き合えるよう支える
- 誠実で信頼できる存在となる
- 助けを求めていない場合でも、必要になったときに支援を受けられることを伝え、本人の意思を尊重する
- 支援の終了にも敬意を持ち、不安を残さないようにする
心的外傷後ストレス障害
(PTSD)の治療
環境の調整
まず、生活環境を整えることが重要です。
PTSDの方は、日常生活が乱れている場合が多く、安心して過ごせる環境づくりや、生活リズムを取り戻すための支援が必要です。症状への具体的な対処方法も、患者様と一緒に考えていきます。
支持的精神療法
ストレスの原因から距離を取れるよう配慮しながら、患者様の話に耳を傾け、否定せず受け止める姿勢が基本です。
安心できる関係性の中で感情を共有し、不安の軽減や安心感の回復を図ります。これにより、世界や他者に対する信頼を取り戻すことを目指します。
薬物療法
SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)が第一選択薬とされています。
これは有効性が高く、副作用が比較的少ないことから、多くのケースで使用されています。日本国内では、パロキセチンやセルトラリンがPTSDへの保険適用を取得しています。また、三環系抗うつ薬ではイミプラミンやアミトリプチンが効果を示すことが報告されており、カルバマゼピンやバルプロ酸といった抗てんかん薬の有効性も確認されています。
なお、抗不安薬が使用される場合もありますが、依存性や耐性(長期使用による効果の減弱)といった問題があるため、長期の服用は原則として推奨されていません。
SSRIとは?
SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)は、脳内のセロトニン濃度を高めることで、抗うつ効果を発揮する薬剤です。
副作用が比較的軽いため、うつ病治療の選択肢を大きく広げた薬剤群として知られています。現在では、うつ病だけでなく、強迫性障害、全般性不安障害、社会不安障害、PTSDなど、幅広い精神疾患の治療に用いられています。
日本で使用されている主なSSRIには以下のようなものがあります。
エスシタロプラム(商品名:レクサプロ)
副作用が少なく、1日1回の服用で済む使いやすい薬剤です。薬物相互作用も少ないため、幅広い患者様に処方されています。
主な副作用としては、吐き気、口の渇き、下痢、眠気、頭痛、めまい、倦怠感、QT延長(心電図の異常)などが挙げられます。
セルトラリン(商品名:ジェイゾロフト)
薬物相互作用が少なく、1日1回の服用で済む手軽さから、臨床で広く使用されています。
日本国内では、うつ病・うつ状態に加えて、パニック障害や心的外傷後ストレス障害(PTSD)への適応も認められています。さらに海外では、強迫性障害や月経前気分障害などの治療にも活用されています。
主な副作用には、吐き気、口の渇き、下痢、眠気、頭痛、めまいなどが挙げられます。
フルボキサミン(商品名:ルボックス、デプロメール
フルボキサミンは、日本で最初に販売されたSSRIで、抗うつ薬としてだけでなく、強迫性障害や社会不安障害の治療にも広く使われる薬剤です。
このお薬は、用量の調整幅が広く、効き方も比較的穏やかなため、単剤で使用する場合には副作用が少ないという利点があります。ただし、肝酵素CYP450(チトクロームP450)に対する阻害作用があるため、併用する薬剤によっては血中濃度が上昇する可能性があり、複数のお薬を同時に使う際には相互作用に注意が必要です。
パロキセチン(商品名:パキシル)
SSRIの中でも特に効果が強いとされており、その反面、副作用の出現頻度がやや高い点も特徴です。
日本では、うつ病・うつ状態に加え、パニック障害、強迫性障害、社会不安障害、PTSDなど、様々な疾患に適応があります。
主な副作用には、吐き気、口の渇き、便秘、眠気、めまいなどが挙げられます。また、他のSSRIでも見られることですが、急に服用を中止すると、離脱症状(めまい、感覚異常、不眠、不安、焦燥感、頭痛、震え、発汗、下痢など)が現れることがあります。そのため、減薬や中止の際は時間をかけて少しずつ調整する必要があります。
暴露療法
認知行動療法の一種で、トラウマ体験を想起させる状況や対象に徐々に慣れていくことで、不安を和らげていく治療法です。
プレイセラピー
子どもの場合、過去に経験した出来事が遊びの中で無意識に再現されることがあります。
プレイセラピーは、こうした遊びを通じて、不安や恐怖などの感情を外に表現し、整理していく方法です。将来的な心理的問題の発生をある程度防ぐ効果があると考えられています。ただし、遊びによってかえって不安が強まり、自分でやめられなくなってしまうような場合には、支援者が物語の展開を「ハッピーエンド」に導く(例:「最終的に助かってよかった」など)ことで、安心して終われるように手助けすることが望ましいとされています。
心的外傷後ストレス障害
(PTSD)の経過
治療を受けた場合、3年ほどで寛解に至るケースが多い一方、治療を受けていない場合は回復までに5年程度かかるとされています。
また、PTSDの患者様のうち、約3分の1は症状が慢性化する傾向があるとも報告されています。
心的外傷後ストレス障害(PTSD)における生活状の注意点
- カフェインを含む飲み物を控えましょう。
- 激しい運動や大きな音がする環境は、交感神経を活性化させて症状を悪化させるため、静かで落ち着ける環境づくりを心がけましょう。










