発達障害について
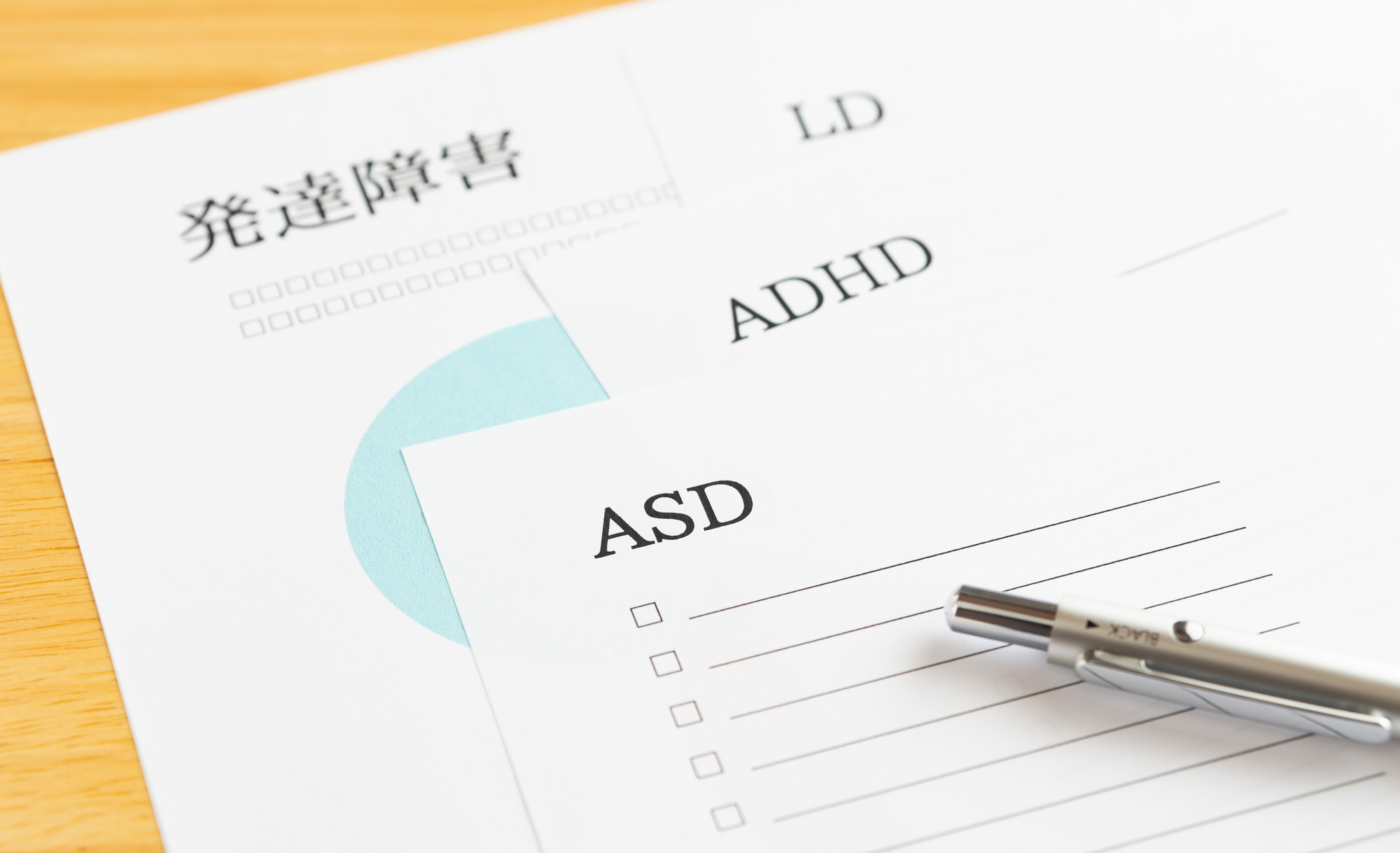 発達障害は、脳の発達に伴って現れる心理的な特性に、生まれつきの遅れや著しい偏り(得意・不得意)が見られる状態を指します。
発達障害は、脳の発達に伴って現れる心理的な特性に、生まれつきの遅れや著しい偏り(得意・不得意)が見られる状態を指します。
例えば、地道な研究を続ける集中力や高い行動力といった得意な面を活かして、社会的に成功を収める方もいます。一方で、注意が続かない、場の空気を読むのが苦手といった不得意な特性によって、日常生活や学校・職場で困難を感じることがあり、これが発達障害とされています。
多くは幼少期から特徴が現れ、成長とともに軽減することもありますが、その特性は一生を通じて続く場合がほとんどです。また、現れ方には個人差が大きいのも特徴です。
発達障害の原因
発達障害の原因はまだ明確には解明されていませんが、主に脳の機能に関わる身体的な要因が関与していると考えられています。かつては「親の愛情不足」や「しつけの問題」といった心理的な要因が原因とされていた時期もありましたが、現在では多くの研究によりこうした見方は否定されています。
発達障害のある人はどれくらいいる?
 発達障害の正確な人数を示す医学的なデータはありませんが、文部科学省が2012年に行った調査があります。
発達障害の正確な人数を示す医学的なデータはありませんが、文部科学省が2012年に行った調査があります。
この調査は、公立の小・中学校に通う通常学級の児童生徒53,882人を対象に実施され、「特別な教育的支援が必要と考えられる発達障害の可能性がある子ども」の実態を把握するものでした。担任教員の観察に基づく結果では、知的な遅れはないものの、学習や行動に著しい困難があるとされた児童生徒の割合は6.5%となっています。
この数字が、国内の発達障害児の実情を示す1つの目安とされています。
発達障害の種類
発達障害にはいくつかのタイプがあり、代表的なものに自閉スペクトラム症(かつては自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害などと分類されていたものを含みます)、注意欠如・多動症(ADHD)、限局性学習症(学習障害)などがあります。これらは単独で現れることもあれば、複数のタイプが重なって見られることも少なくありません。そのため、同じ診断名であっても、お子様によって特性の現れ方が全く異なって見える場合があります。
発達障害の治療
 発達障害は「治す」ものではなく、その人が持つ特性の1つと捉えられています。大切なのは、ご本人やご家族、周囲の方々が特性を正しく理解し、その人に合った方法で生活環境を整えることです。そうすることで、本来の力を発揮しやすくなり、自分らしい生き方を築いていくことが可能になります。こうした取り組みは、うつ状態や不登校、ひきこもりといった二次的な問題の予防にも繋がります。
発達障害は「治す」ものではなく、その人が持つ特性の1つと捉えられています。大切なのは、ご本人やご家族、周囲の方々が特性を正しく理解し、その人に合った方法で生活環境を整えることです。そうすることで、本来の力を発揮しやすくなり、自分らしい生き方を築いていくことが可能になります。こうした取り組みは、うつ状態や不登校、ひきこもりといった二次的な問題の予防にも繋がります。
当院では治療の一環として、カウンセリングを行うことがあります。対話を通じて課題を明確にし、患者様と治療者が一緒により良い対応策を考え、実際に取り組みながら次回の面談で振り返る、という方法です。これにより、学校や日常生活の中での具体的な困りごとに対する対応力を少しずつ身につけていきます。
また、薬物療法が有効なケースもあります。注意力の向上や多動・衝動性の軽減、刺激への過敏な反応を抑えるためのお薬が用いられることがあります。例えば、授業中に席に座っていられなかったお子様が、服薬によって落ち着いて授業を受けられるようになり、学習の遅れを防げる場合もあります。ただし、お薬には副作用の可能性もあるため、毎日服用するのか、特定の科目のある日に限定するのかなどは、主治医としっかり相談して決める必要があります。
当院ではこうした多様な治療方法をご用意しています。まずはお気軽にご相談ください。










